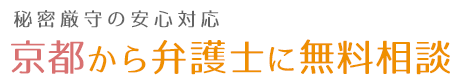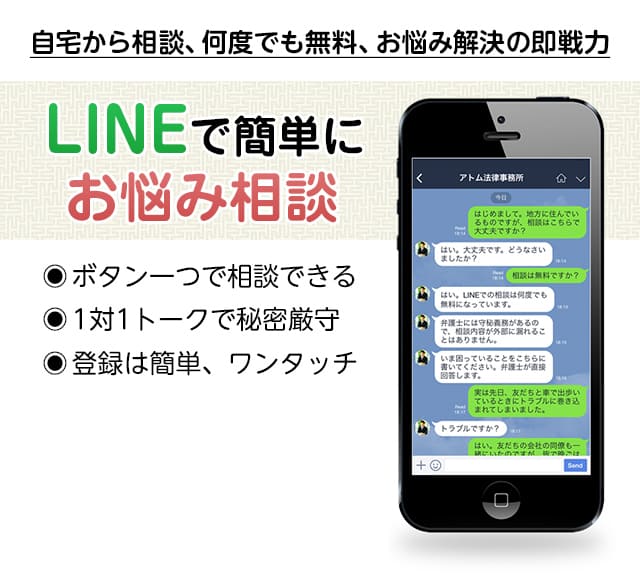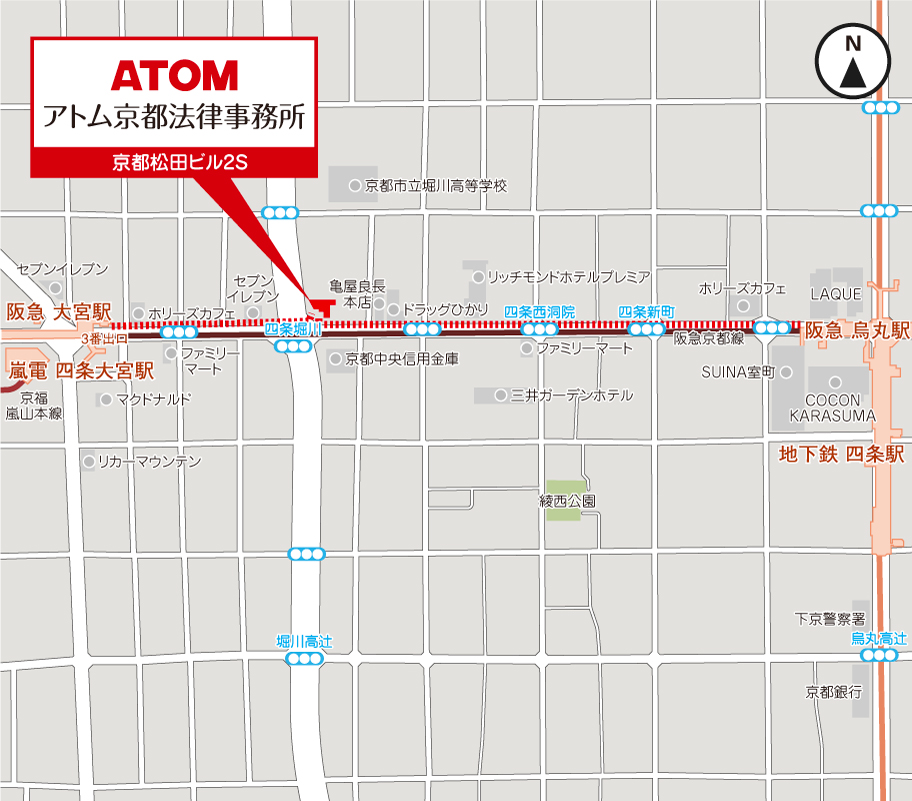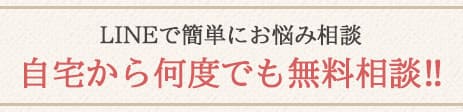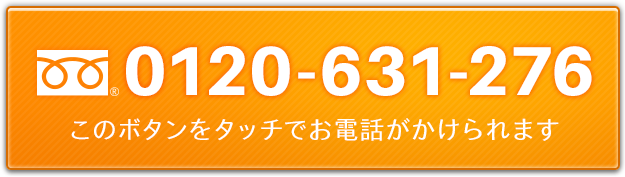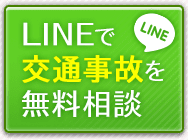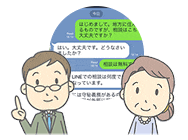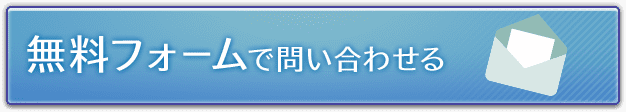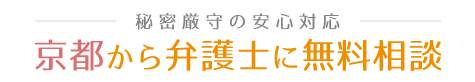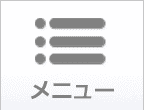弁護士がまとめた「賃料増額・減額」のQ&Aです。
Q 賃料増額・減額とは何ですか?
短期間しか入居しないような形態では問題となることは多くありません。たとえば、学生、一人暮らしのアパート等の契約などです。
しかし、長期間にわたって入居又は土地等を借りるケースでは、賃料増額・減額が問題となることもあります。
たとえば、家族で住む場合のアパート契約であれば、賃貸期間が長期間となる傾向があります。また、土地を借りて、土地の上に家を建てる場合も、長期間となる傾向があります。さらに、事業者(テナント)が、土地又は建物を借りる場合、経営が順調であれば長期化することが多くあります。
賃貸借契約の期間が長期間になればなるほど、お互いにとって事情の変化があり、賃料の改定が必要となるのは当たり前のことです。
Q 賃料増額の手順は、どのような形になりますか?
当事者での交渉では、できる限り円滑・円満に、賃料増額が実現される方法をとることが必要となります。当事者の間での解決ができない場合、裁判手続等をとることになりますが、裁判手続等は費用対効果の点でデメリットとなることがあるからです。
たとえば、賃貸期間が終了した後、更新の際に、賃貸人が、賃料増額の話をすること等が行われています。
当事者の間での解決ができないケースでは、調停手続を利用する必要があります。調停では、第三者が仲裁してくれますので、借主も応じやすくはなります。
ただし、調停まで進んでしまうと、借主もしっかりした賃料増額の根拠がなければ応じない可能性が高くなります。そのため、近隣の賃料の調査、不動産鑑定士の意見等、賃料増額の根拠の説明が必要となることが多いでしょう。
調停で合意できないケースは、民事裁判手続で解決することになります。民事裁判手続では、証拠や法律上の根拠が必要となるため、弁護士に依頼する必要が高くなります。また、不動産鑑定士への鑑定費用など費用面も重くなることもあります。
Q 賃料減額のケースはありますか?
貸主側と異なり、借主側は、賃料が安い別の物件を借りることが比較的容易です。
また、最近では、一部の都市部を除き、賃貸物件の空きが目立っています。貸主は、一層、賃料を維持する競争力の低下にさらされています。
このような状況のため、当事者の交渉で、貸主が賃料減額を同意することも多くなってきています。