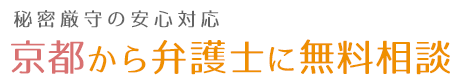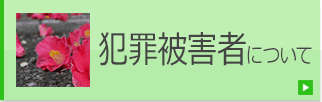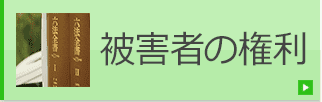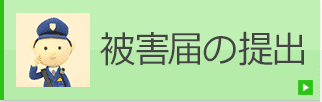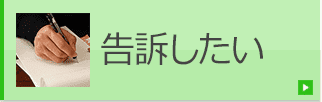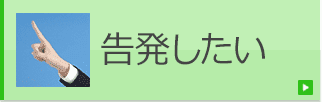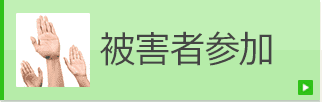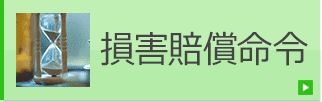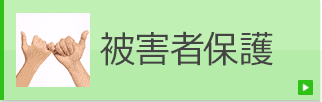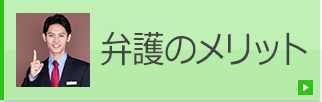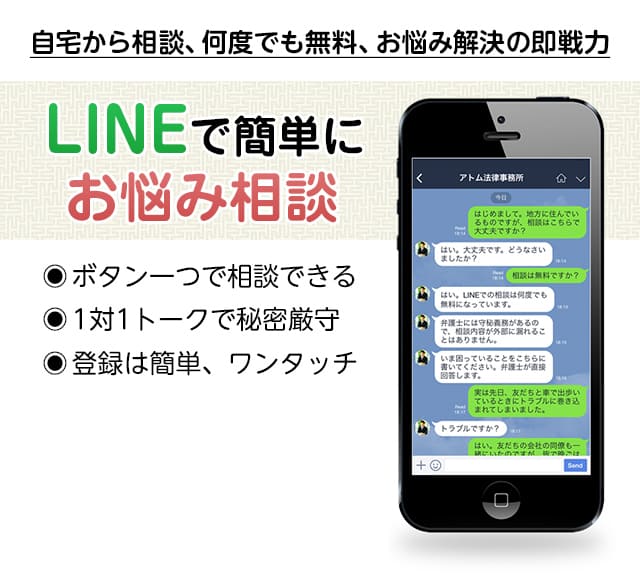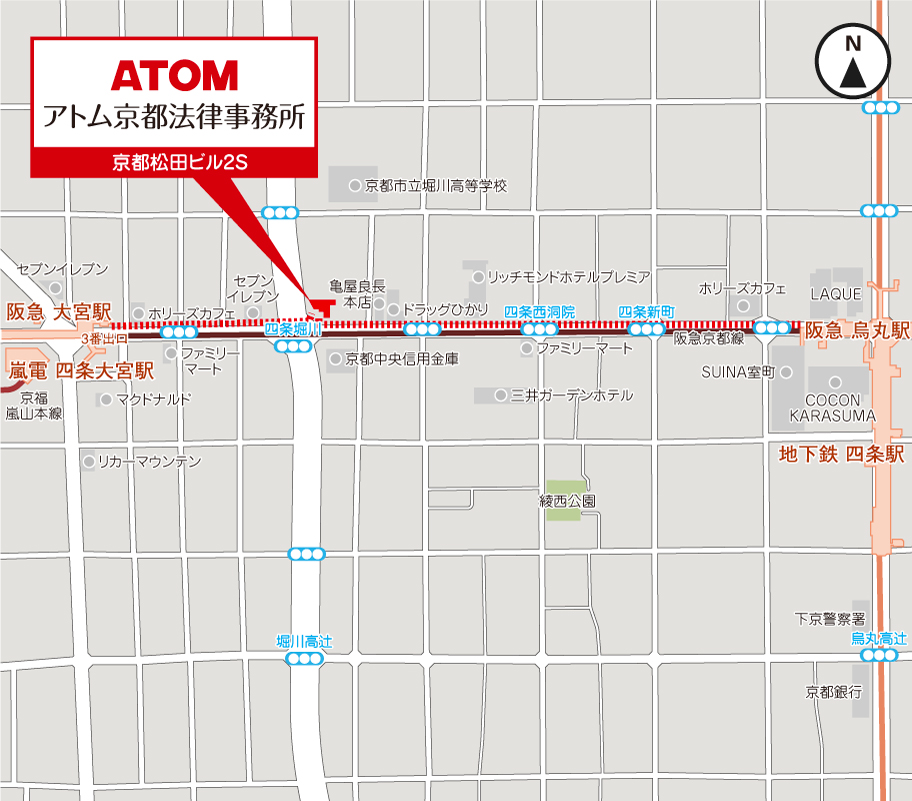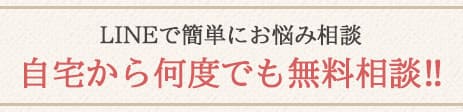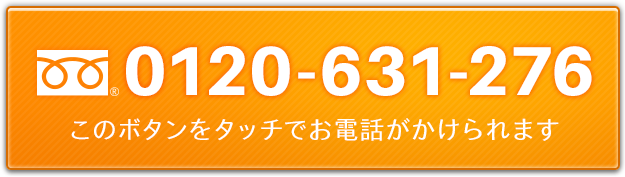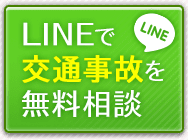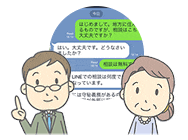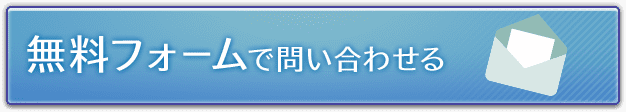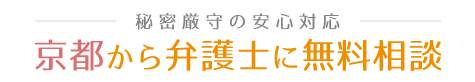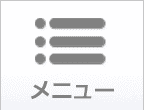「被害者保護」に関するQ&Aを弁護士がまとめました。
Q 被害者保護の制度はどのようなものがありますか?
犯罪被害者保護法(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律)には、1.裁判の優先的傍聴、2.刑事裁判の記録の閲覧・コピー、3.刑事和解、4.損害賠償命令制度が定められています。
Q 被害者は、裁判を傍聴できるのですか?
また、傍聴希望者が多いことが予想される事件では、あらかじめ被害者または遺族らから申出があった場合、優先的に傍聴席が確保されるよう、できる限りの配慮がなされます。
Q 被害者は、刑事記録の閲覧・謄写ができるのですか?
裁判中の刑事事件については、原則として、一般の方が刑事記録を閲覧したりコピーしたりすることはできません。しかし、被害者または遺族らが事件の内容を知りたいと思うのは当然の気持ちです。
そこで、被害者または遺族らから裁判所に対して申出があった場合には、原則として、刑事記録を閲覧したりコピーしたりできることになっています。
また、その事件と同種の犯罪行為の被害者の方(同種余罪の被害者)は、検察官に申出をして、刑事記録を閲覧したりコピーしたりすることができます。例えば、振り込め詐欺事件などで利用が可能です。
Q 被害者保護法にある刑事和解とはなんですか?
つまり、示談どおりに支払がなされない時に、強制執行が可能となります。民事裁判を行わずに簡易かつスピーディーな被害回復を目指す制度です。
Q 被害者保護法にある損害賠償命令制度とはなんですか?
損害賠償は、通常民事裁判ですので、刑事裁判の判決を言い渡した裁判所で審理を行うことはできません。しかし、刑事裁判とは別に民事裁判で損害賠償の請求をすることは、被害者にとって負担が大きいため、特別に刑事裁判を行った裁判所と同じ裁判所が損害賠償の審理を行うことができます。
損害賠償命令制度は、被害者が簡易かつスピーディーに被害回復できるようにするために設けられた特別な制度です。原則として、4回以内の審理で結論が出ること、刑事裁判の成果を利用できるなどの特徴があります。
Q 法廷で証言するのが不安な場合、保護制度はありますか?
まず、「証人への付添い」があります。証言の間、家族や心理カウンセラーなどが、証人のそばに付き添うことにより、証人の不安や緊張を和らげることを目指しています。
次に、「証人の遮へい」があります。証人が被告人や傍聴人から見られていることで心理的な圧迫を受けるような場合に、証人と被告人や傍聴人との間についたてなどを置き、被告人や傍聴人の視線から証人を保護します。精神的負担を軽くすることを目指しています。
また、「ビデオリンク方式による証人尋問」という方法もあります。証人は別室にいて、法廷と別室とをテレビ回線で結び、モニターを通じて尋問を行う証人尋問の方法です。性犯罪などにおいて、法廷での証言が精神的負担となる場合に有効です。
Q 被害者参加制度とはなんですか?
被害者参加制度の対象事件は刑事訴訟法で定められています。殺人罪、傷害致死罪、危険運転致死傷罪、強姦罪、強制わいせつ罪、逮捕・監禁罪、過失運転致死傷罪などです。
Q 法廷で氏名や住所などを明らかにしないでもらえますか?
性犯罪などの場合、公開の法廷で被害者の氏名や住所などが明らかにされると、被害者に二次的被害が生じるおそれがあります。そこで、一定の犯罪においては、被害者の申出により、氏名などを明らかにしないことが認められます。
Q 被害者保護の制度を利用する場合、弁護士を依頼するメリットはなんですか?
弁護士をつけなくても、さまざまな被害者保護の制度を利用することは可能です。しかし、刑事裁判は一般の方にはなじみがない手続きですし、被害者として身体・精神にダメージを受けた状態で、ご自身のみで制度を利用することは大変だと思います。
そこで、弁護士をつければ、専門的な手続きについて任せることができ、ご自身の意見を反映させるためのサポートを受けたり、不安や緊張を和らげる制度を利用したりできます。