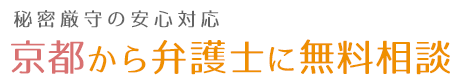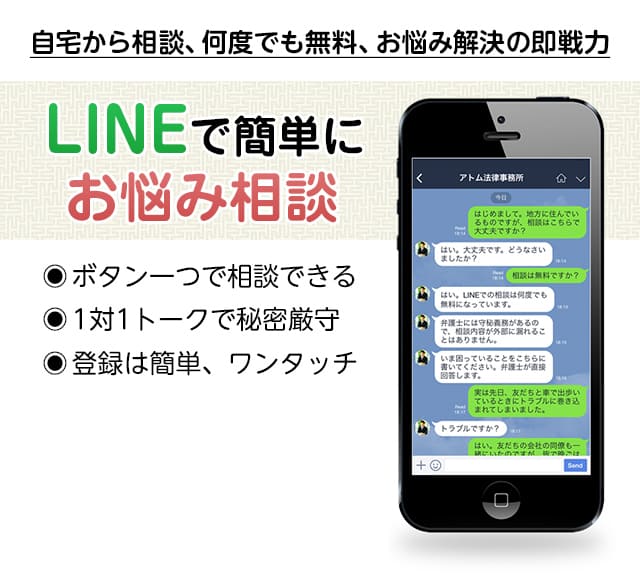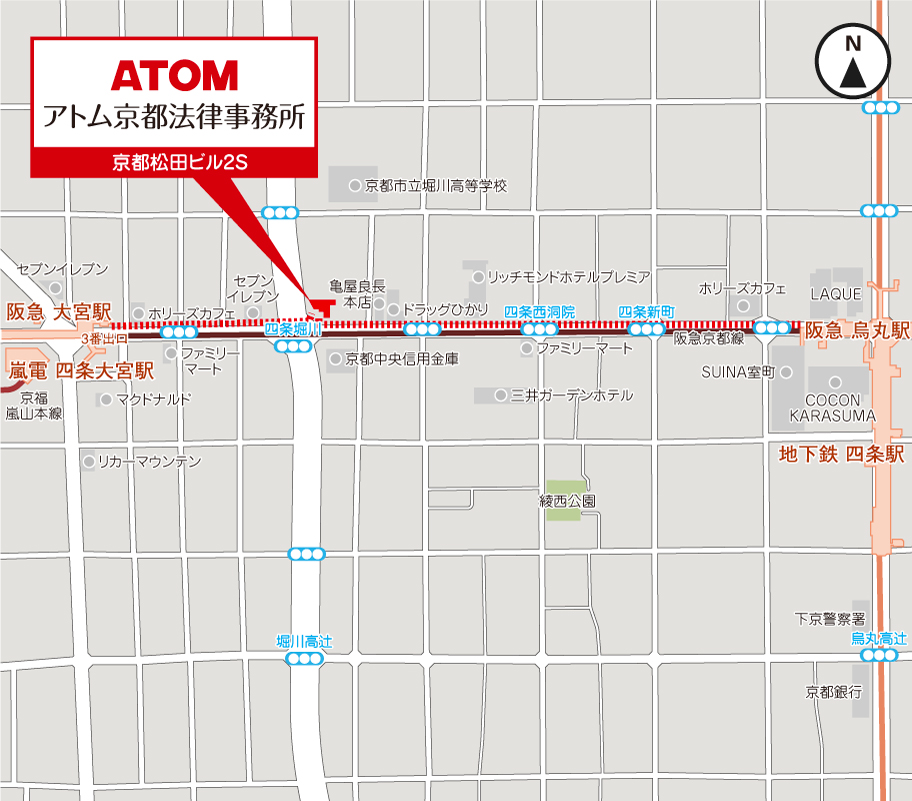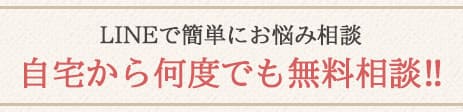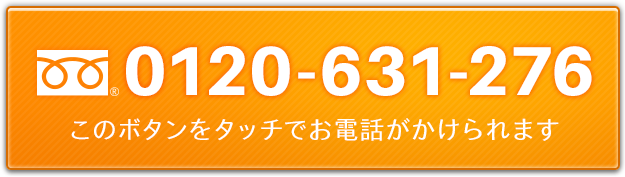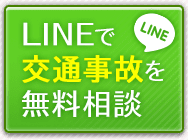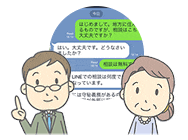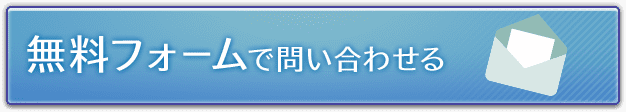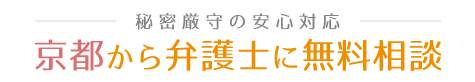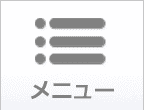弁護士がまとめた「パワハラ」のQ&Aです。
Q 上司は指導・教育といいますが、パワハラだと思います。パワハラとは?
業務命令とされていても、パワハラにあたる場合もあります。また、退職強要・退職勧奨もパワハラにあたる場合があります。
パワハラとは、職場での地位や権限を利用して部下の人格を侵害する行為です。パワハラにあたるかどうかは、ケースバイケースの判断となります。
パワハラを受けると、心身ともにまいってしまいます。会社内で相談しても、改善されないことも多いです。パワハラがエスカレートすることすらあります。しかし、諦める必要はありません。弁護士に相談すれば、解決の道筋が見えてきます。
Q パワハラを受けている場合、どのような請求ができますか?
損害賠償請求は、加害者である上司に対してできるのはもちろん、「事業の執行について」行われた場合には、会社に対してもできます。
また、会社は、労働者が安全に労働できるように配慮する義務がありますが、パワハラが横行するような職場環境を改善しないでいることは、会社にその義務違反があります。その責任を追及することも可能です。
損害賠償請求の方法は、労働審判や裁判です。損害としては、精神的苦痛に対する慰謝料、パワハラで退職しなければ得られた賃金相当額、パワハラで通院が必要となった場合の治療費などが請求できます。
また、現在もパワハラが続いている場合には、差止請求も可能です。差止請求の方法は、仮処分や労働審判です。差止めにより、職場の環境が改善する可能性が高いです。
労働審判、裁判、仮処分には法的な専門知識や技術が必要となります。弁護士に依頼すれば、パワハラで受けた損害について金銭請求ができ、現在続くパワハラを止めさせることも可能です。つらい気持ちをかかえて泣き寝入りする必要はありません。
さらに、パワハラが刑法にふれるような態様の場合には、刑事告訴も可能です。また、労災が認定される場合もあります。
Q パワハラを争う場合の問題点はなんですか?
パワハラがあったことを証明するのは、ご依頼者の側です。証拠としては、例えば、パワハラを受けたことを記したメモや日記、パワハラを受けている場面の録音や動画、パワハラを示すメール、医師の診断書などです。なお、民事では、こっそり録音した場合であっても証拠として認められます。
また、パワハラをやめるよう加害者と会社に内容証明郵便で申し入れることも、パワハラが会ったことを示す証拠になります。
十分な証拠がないと思っていても、弁護士に相談すれば、立証の困難を打破できる工夫が見つかることがあります。
Q パワハラで労災の請求はできますか?
パワハラにより、うつ病になって働けなくなってしまったり、自殺に追い込まれてしまう悲しいケースがあります。従来の労災認定基準は、精神疾患についてとても厳しい基準でした。平成23年に基準が改正され、従来に比べ、精神疾患の労災認定が認められやすくなりました。
労災認定を争う場合、審査請求、再審査請求という行政不服審査の手続きがあります。それでも認められない場合には、行政訴訟ができます。労災認定をとるため、諦めずに弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
また、労災による補償を受けていても、全ての損害がカバーされているわけではありません。損害賠償請求も可能な場合があります。